WEBコラム〈17〉外国籍住民としてみてきた国際交流と多文化共生

Bettina Gildenhard (ベティーナ・ギルデンハルト)
同志社大学 グローバル・コミュニケーション学部 准教授
以前には国際交流のイベントに参加した際、一種の居心地悪さを覚えることが多かった。たくさんの民族衣装や踊りが披露される中、「ドイツ人」として招かれた自分が、その「ドイツ人らしさ」をどのように演出したらいいか常に悩んでいたからだ。たしかにドイツでは地域ごとに民族衣装のような服装が存在するものの、私は着たことがないし、歌と踊りという特技もない。そんな私は少しずつ国際交流のイベントを敬遠し、批判的に捉えるようになってきた。欧米で指摘される3F-fashion, food, festival-の多文化主義 、つまり取っ付きやすいものにだけに注目する、うわべだけに留まる多文化主義が、日本における国際交流にも当てはまるような気がした。昔の万国博覧会のように外国のものが見世物扱いされ、外国の人・モノは気持ちよく消費される。イベントが終われば、交流も終わってしまう。また、我々(内国人) vs 彼ら(外国人)という二項対立的な枠組みで行われる国際交流では、交流どころか、かえって高い垣根が作られてしまう場合さえあるのではないか。
こういった批判的な考え方を見直すきっかけとなったのは、○○市の国際交流協会からドイツ料理の調理教室を頼まれたことだった。最初はしぶしぶだったが、伝えたいことを伝えるいいチャンスだと私は気付いた。「ドイツ料理」ではなく、南ドイツの家庭料理を作り、エルザスの伝統的な加工食品でもある「シュークルート」と越境的な食材である「ジャガイモ」に焦点を当て、また現在のドイツではトルコ由来の「ケバブ」が欠かせないものだということも伝えれば、ドイツの地域性、移民国ドイツの様子を紹介しつつ、「国を単位とする」思考の枠組みを少しでも変化させることができるのではないかと考えたからだ。実際、国際理解協会のボランティア・スタッフと何回も打ち合わせをして、イベントも一緒に企画することになった。このプロセスは楽しいもので、総務省の「地域における多文化共生推進プラン」で強調されている「対等な関係性」はこのように築かれるのだと実感できたような気がした。イベント自体も楽しかったし、自分が「ドイツ人!」としてではなく、また「客寄せパンダ」とか「教材見本」としてではなく、一人の生きた個体として認識された気がしたものだった。
現在、私は「国際交流」のイベントを「入り口」として捉えている。外国籍住民を単なるお客さんとして呼んだだけでは、せっかく開いた扉がイベント終了後には再び閉まってしまう。だが、企画の過程も重視し、お互いの思いに耳を傾ければ、対等な関係性を築いていく格好の機会にできる。国際交流イベントが「入り口」なら、多文化共生は入り口の向こうにある「シェアハウス」だと私は思っている。学生の頃にシェアハウスに住んだ経験がある。ドイツ人同士でも、ゴミ出しや掃除などに関して、小さないざこざが絶えなかったが、そこでコミュニケーションとルール作りの大切さを学んだ。全体的に楽しい期間だったし、日頃の共同生活を通じて、お互いを理解できるようになった。
多文化共生にはイベントのような華やかさはないが、「共生」の基盤は地味な日常であり、地域の日本語教室やスポーツサークルなどの方がお互いの心理的な垣根を低くできる。多文化共生を実感・実践できる場となり得ると考える。そこでの出会いは、外国籍と日本人住民の相互理解を深めるためのもっとも有効な「啓発教材」の一つだ。定期的に顔をあわせることで、お互いを生きた個体として認識できるようになり、名前のない「あの○○人、あの○○国の人」は「○○さん、△△ちゃん、××くん」に変わるからである。
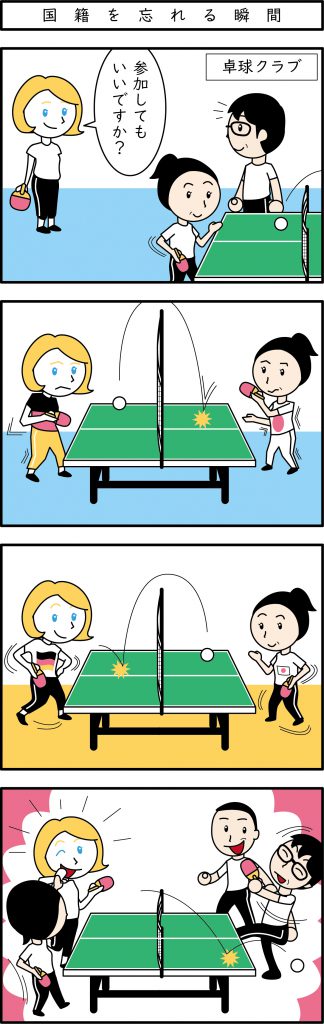
● 草の根多文化共生創作の集い
https://www.facebook.com/tabunkakyouseitudoi
https://www.instagram.com/kusanone.tabunkakyosei/






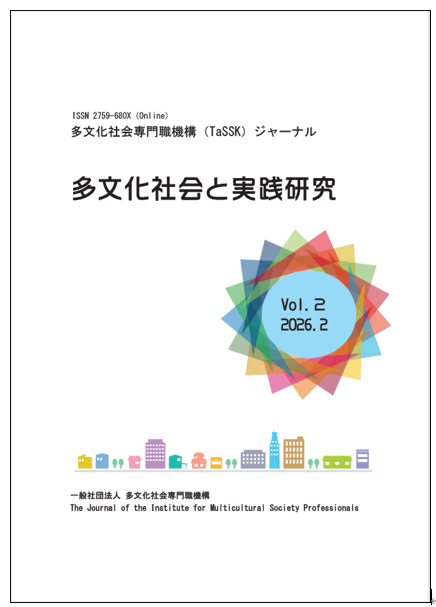

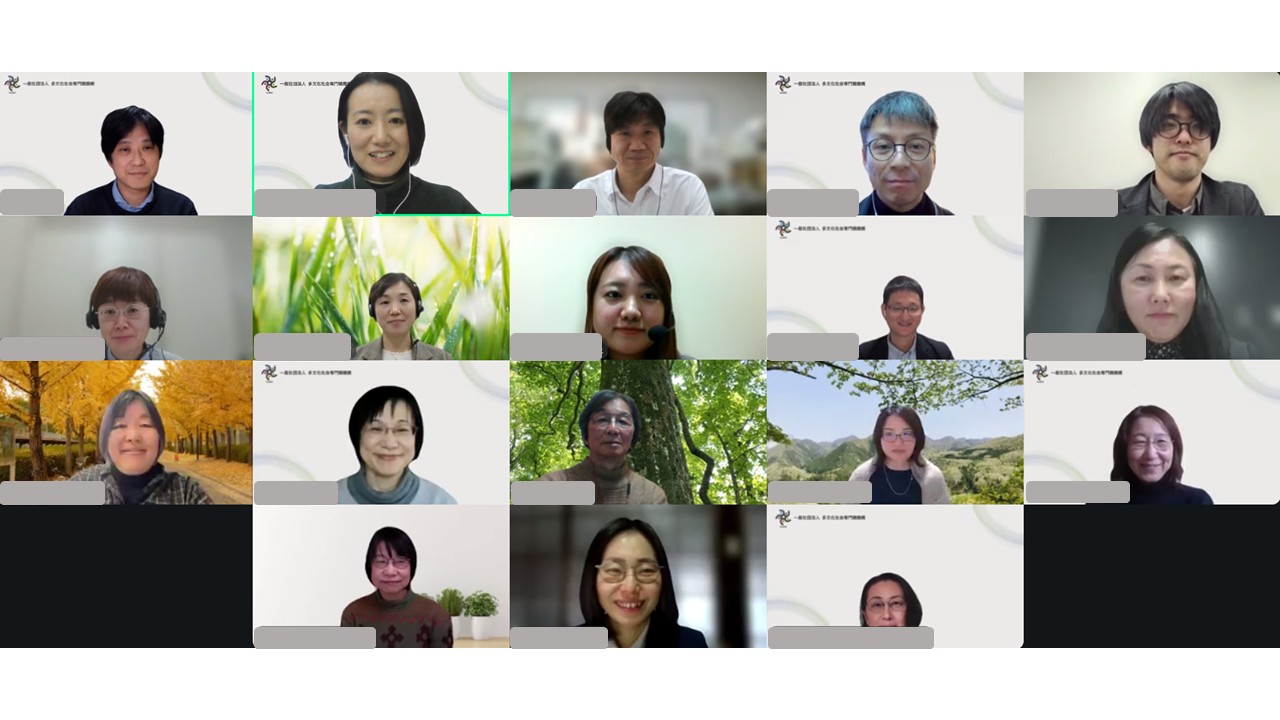
-scaled.jpeg)
