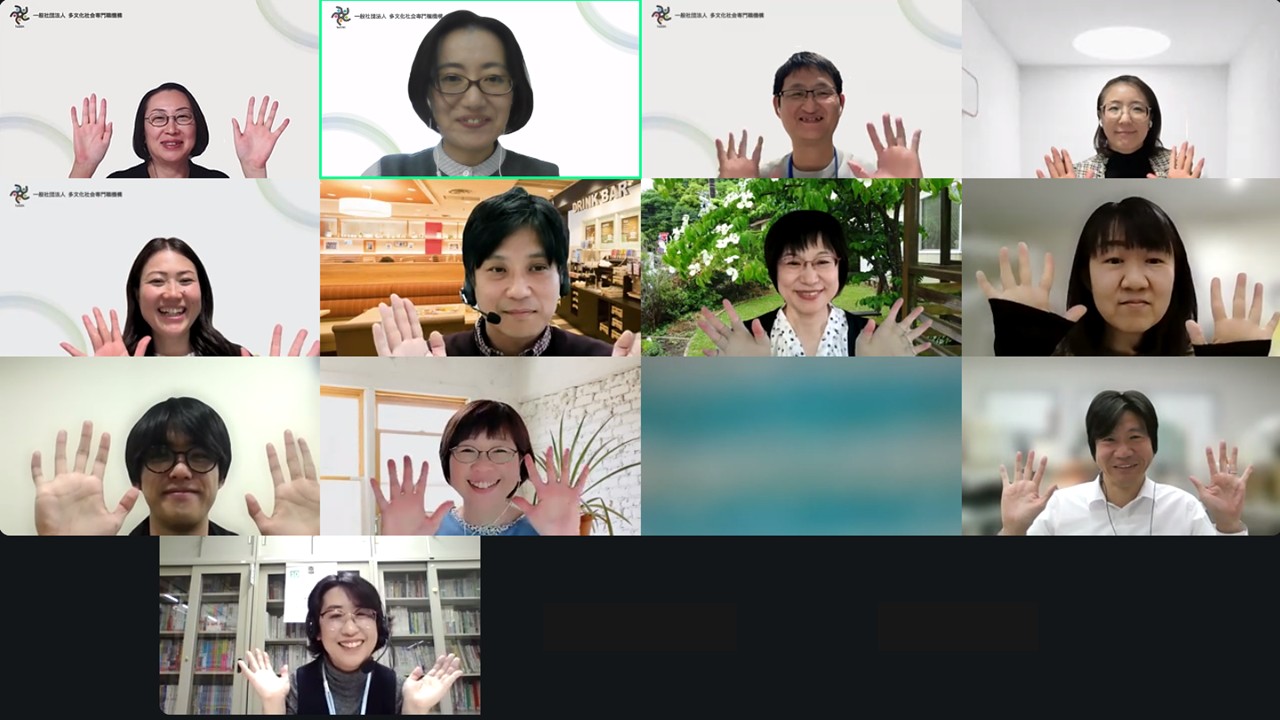【参加者募集!】第9回多文化社会実践研究フォーラム 「南九州発 地域から多文化社会・多文化共生を問う」
多文化社会専門職機構の実践研究フォーラムでは 、第3回以降 、中期的テーマとして、「多文化社会における市民活動と専門職 」(第 3 回~第 5 回 )、「難民 ・避難民への対応と多文化社会の課題 」(第 6 回~第 7 回 ) を設定してきましたが 、第8回以降は、「 地域から多文化社会 ・多文化共生を問う」を中期的テーマにすることにしたいと思います。グローバルなレベルで多文化化が急速に進む一方で 、それぞれの地域では 、風土や地域文化との関連の中で 、多文化化がどのような社会状況や共生関係を具体的に生み出しつつあるのか 、その過程での課題とは何か、などについて問うことを目的とします 。
第9回は外国人住民の増加率が全国でも高い南九州で開催します。本フォーラムを地域で開催することで、大都市で開催される都市型のフォーラムではなく、小規模でも地域の実情に即した、 地域を実感するTaSSK型のフォーラムを開催したいと思います。※10/31発表者、登壇者情報を更新しました。
[日 時]2025年12月13日(土)14:30~18:00/12月14日(日)9:00~13:00
[会 場]綾川荘奥座敷大広間(宮崎県東諸県郡綾町北俣3765)https://ayakawasou.com/
[主 催]一般社団法人 多文化社会専門職機構(TaSSK)
[定 員]30人(先着順。事前申込みが必要です)
[対 象]
・自治体、国際交流協会、社会福祉協議会などで多文化共生施策に携わる職員
・日本語教育、法律、医療、福祉などの各分野で多文化社会に関わる専門職
・コーディネーター、相談・コミュニティ通訳者などの多文化社会専門職
・その他、多文化社会に関心のある方ならどなたでも
[参加費]
○TaSSK会員 4,000円
※TaSSK入会についてはこちらをご覧ください http://tassk.org/admission
◎非会員 5,000円
◎宮崎県在住者 2,000円
◎学生 1,000円
[申込方法]申込みはpeatixのみとなります。ご了承ください。
申込みはこちらから
※お申込後の返金には応じられませんので、予めご了承ください。
※受付は先着順となります。定員に達し次第、申込みを締め切ります。
【申込締切日:12月5日(金)】
〈重要なお知らせ〉【申込は終了しました】の綾川荘に宿泊が可能です。宿泊・懇親会に関する案内・受付はこちらのサイトで行なっています。【宿泊・懇親会の申込締切:11月28日(金)】
☆本フォーラムのチラシはこちらをご覧ください。
【プログラム】
◎1日目 12月13日(土)14:30-18:10
◾️ラウンドテーブル 14:30-17:10
・14:30-14:45 オープニング
14:45-15:30 ① 「カフェを起点として宮崎でのコミュニティづくり」
・発表者:ロッキー ヴァン氏(6ラクーン カフェ ソサエティ共同経営者)
カナダ トロント出身。東京出身の友人・田中さんと宮崎でカフェを共同創業。世界中の美味しい料理と多様な文化を体験できるカフェを通して、地元住民と外国人を結ぶ拠点づくりについてお話します。
15:35-16:20 ② 「思いと共感がつながりをつくる」
・発表者:新宮 有子
(霧島ヒスカル日本語教室日本語ボランティア /都城市沖水地区市民センター所長 )
多文化共生事業に必要なのは、外国人市民のニーズに寄り添いながら周りの人を巻き込んでウインウインな関係を築いていくこと。私の身近で起きている事例をご紹介し、いかにして行政や地域住民が連携して外国人市民が住みやすい地域づくりを進めていくか、みなさんと一緒に考えたい。
16:25-17:10 ※発表③と④は同時に行われます。
③「入管政策をめぐる『声の届け方』と市民の実践 」
発表者:髙栁香代(移住労働者と共に生きるネットワーク・九州 会員)
福岡出入国在留管理局とNGOとの意見交換会の記録を手がかりに、九州内の外国人の生活・労働相談の現場から「当事者の声」を地方入国管理局へどう届けてきたかを考える。その過程に見える、ネットワーク型で展開する市民活動と地方入国管理局との関係性の構築や市民運動の質的変化について、本ラウンドテーブルで参加者と語り合いたい。
④「協働か下請けか? NPOと行政の『協働』現在地を語れ」
発表者:奈良雅美(特定非営利活動法人アジア女性自立プロジェクト 代表理事)
某市当局からの打診を受け開始した外国人保護者向けのガイダンス委託事業。双方の協働スタンスを確認していたが、ことはそう簡単に動かないこともあり。TaSSK的コーディネーション視点で振り返りながら、NPOと行政の協働の現在地を参加者と語りあう。
◾️実践研究発表17:15-18:00
発表① 「地域日本語教室/日本語活動における非対称な関係性の捉え直し―「聞く姿勢」に焦点をあてた試み―」
発表者:中野玲子((一社)kaigoと日本語つむぎの会)、和田貴子(ことばプロジェクト /一社)HORIZOPIC)
地域日本語教室/日本語活動の実践をとおして、非対称な関係性の捉え方を問い直す。発表者2名は、参加者間の関係性に変容を起こすために、「聞く」に焦点をあてた試みを行った。実践をもとにした非対称な関係性について報告する。
発表②「個人の出会いからコミュニティづくりへ発展する「場」をつくるコーディネート」
発表者:松岡真理恵((公財)浜松国際交流協会)
多文化社会におけるコモンズとして、様々な背景の人が出会い交流する「これからバディ」活動。国や言語、在留資格、社会的立場などを横に置いて個人が出会い、コミュニティづくりに発展する「場」として機能するためのコーディネートを考える。
◎2日目 12月14日(日)9:00〜13:00
◾️9:00-10:00 セミナー「お茶の個性の引き出し方」
講師:白尾 尚美 氏
NPO法人日本茶インストラクター協会認定/日本茶シニアインストラクター/宮崎県煎茶手もみ保存会 会長/白玄堂茶屋 店主

◾️10:15-13:00 全体シンポジウム
「[南九州発]地域を耕す 未来を創る 外国人住民が拓くしなやかなコミュニティの可能性」
【登壇者】
ヨハネス・ヴィルヘルム氏
JICA九州国際協力推進員(KUMAMOTO KURASU事務局長)
昭和45年生東京まれのドイツ国籍。南阿蘇村に住みながら熊本県庁でJICAの推進員としてKUMAMOTO KURASUの事務局長をしている。本来は日本地域社会の研究者。これまで、地域おこし協力隊として多文化共生推進に関わってきた。
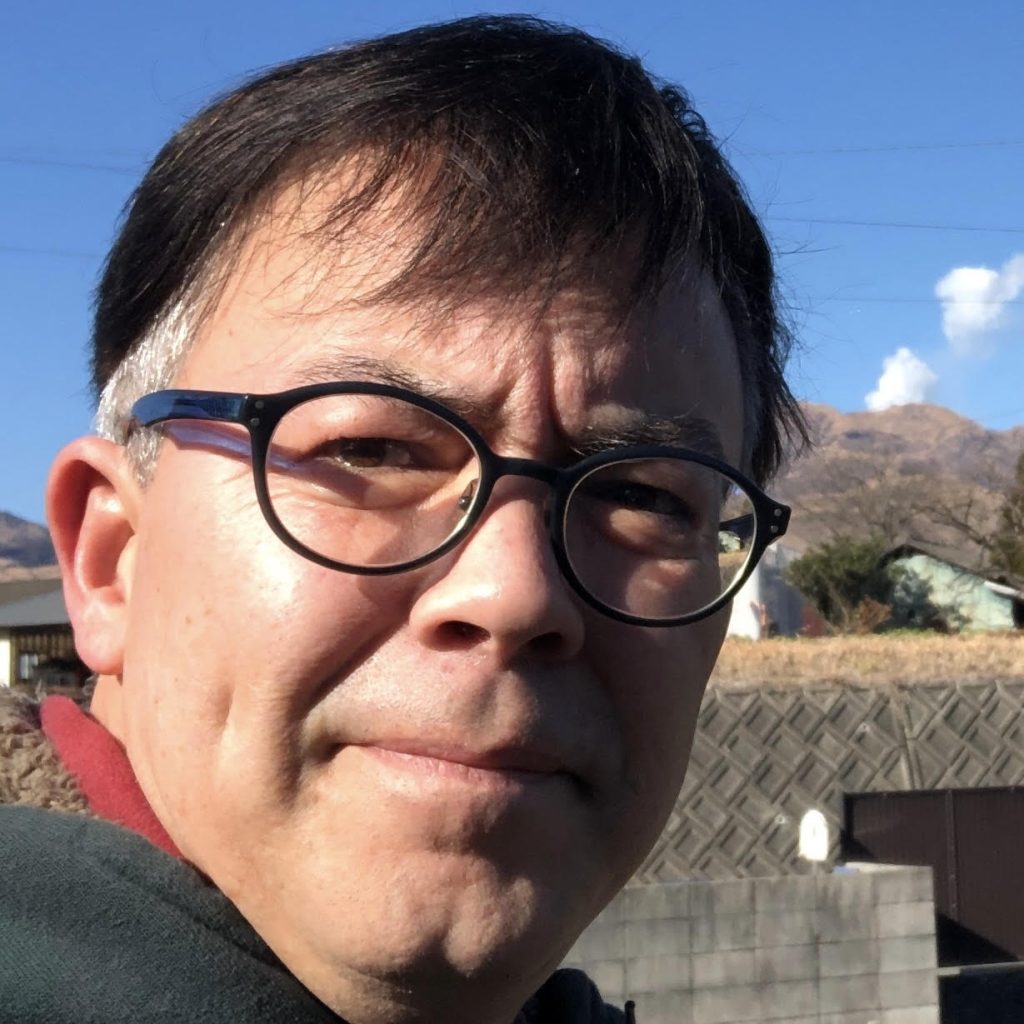
Nurhayati(ヌルハヤティ)氏
まちんなか国際交流会 インドネシア語通訳者
インドネシア・東ジャワ出身。日本在住歴は10年以上となった。東京で日本語学校に通った後、茨城県の日本企業で勤務し、インドネシアにある関連工場との架け橋としての業務に従事した。現在は宮崎市で子育てをしながら、通訳者として様々な場と人をつないでいる。

サイエット・ケンジ氏
宮崎国際大学 グローバル教育センター
宮崎国際コミュニティ 会長
宮崎イスラミックソサエティ 会長
宮崎国際大学グローバル教育センターにて英語教育やICT活用に携わっている。25年以上の翻訳・通訳経験を持ち、国際交流や異文化理解の促進に尽力し現在、宮崎国際コミュニティおよび宮崎イスラミックソサエティの会長として、地域社会と世界をつなぐ活動を続けている。

[ファシリテーター]髙栁香代(TaSSK認定多文化社会コーディネーター、宮崎県多文化共生アドバイザー)
国際交流協会のスタッフとして勤務する傍ら、市民団体で長年、外国人住民の生活相談や地域日本語教育の活動を続けている。また近年では人材育成等に取り組みながら、多様な背景を持った人たちとの地域づくりを目指している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]一般社団法人 多文化社会専門職機構(TaSSK)
Tel:(03)6261-6145/ Email:tasskforum(at)tassk.org
URL: http://tassk.org/
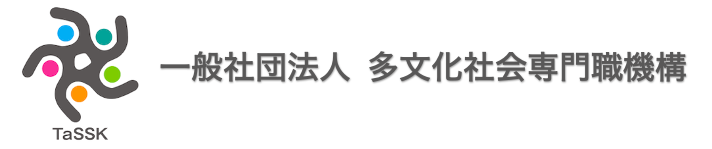

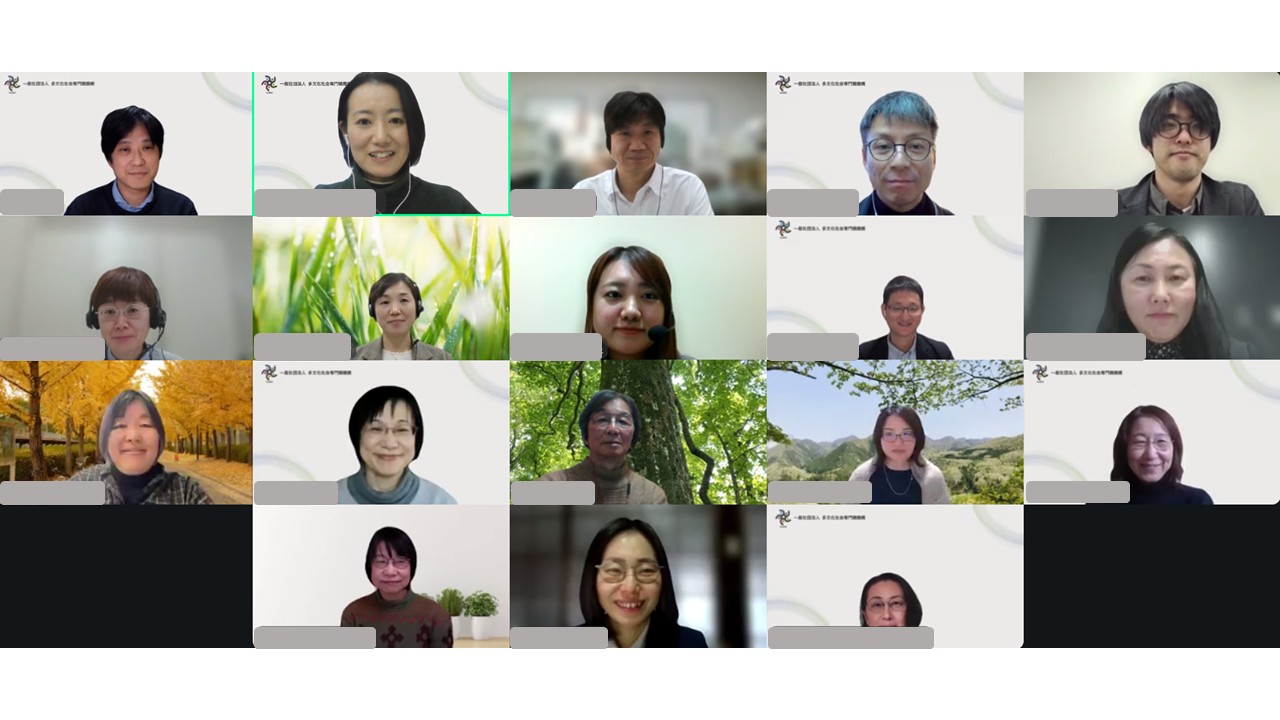
-scaled.jpeg)